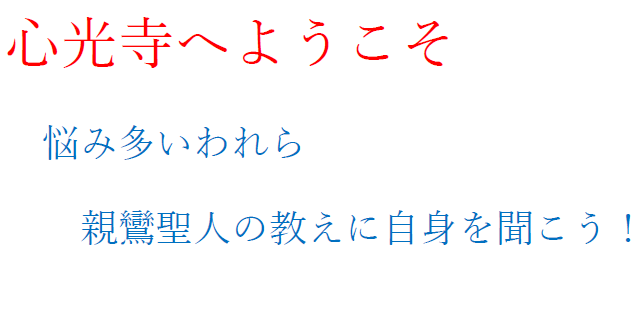No7-「すなわちわれらなり」の呼び声
- bunryu
- 2022年3月1日
■親鸞聖人が、『尊号真像銘文』の中で「すなわちわれらなり」と述べておられる言葉があります。短い言葉ですが、非常に重要な言葉で、私は、この言葉の中に、親鸞聖人が法然上人から受け取られた念仏の救いの内容の要が収まっているのではないかと思います。そのことについて、今感じていることを少し書いてみたいと思います。
この言葉は、『尊号真像銘文』の中に、次のようなかたちで述べられています。
「『十方衆生』というは、十方のよろずの衆生なり。すなわちわれらなり」
(親鸞聖人『尊号真像銘文』(真宗大谷派『真宗聖典』521頁)
「『十方衆生』というは」というのは、『無量寿経』の中で法蔵菩薩が、第十八願、第十九願、第二十願の三願にわたって、三度われらを「十方衆生よ」と呼びかけておられます。その「十方衆生とは…」ということです。それについて、「『十方衆生』というは、十方のよろずの衆生なり」と述べておられるのです。これは、同じ言葉を繰り返しているだけのようにみえますが、最初の「十方衆生」は経典の言葉を指していて、次の「十方のよろずの衆生なり」というところで、その言葉についての親鸞聖人の受け止めが述べられているわけです。 「よろずの衆生」という言葉には、親鸞聖人の特別な思いがこめられているように思われます。親鸞聖人は、『唯信鈔文意』の中にも、
「『分』は、わかつという、よろずの衆生ごとにとわかつこころなり」(真宗大谷派『真宗聖典』547頁)
というふうに、「よろずの衆生」という言葉を使っておられます。「よろずの衆生」ですから、色んな人がいるということです。千差万別で、皆一人一人違います。一人として同じ人はいません。その無数の数限りない衆生それぞれが、それぞれの苦しみや悲しみを抱えて、心に怯えを抱きながら生きています。「一切恐懼為作大安」(『真宗聖典』12頁)と『無量寿経』に述べられているように、法蔵菩薩の眼から見れば、一切の衆生は、意識しているといないとにかかわらず、一人残らず心の深い所に怯えを抱いていない者はいないのです。
■先日、朝日新聞の「悩みのるつぼ」という相談コーナーに、「幼少期から、自己肯定感なく生きてきました」という相談を寄せられている方がおられました。人は、程度の差こそあれ、自分自身について十分な自己肯定感を持ちえないまま生きている人は多いと思います。
平野修師は、
「『大経』(『無量寿経』のこと)でいわれている、『庶類』・『群萌』は、その存在のありさまが、あたかも世界の中に埋没したかのように置かれているか、あるいはそうなるように余儀なくせしめられている存在といってよいでしょう。したがって自己同一がどこにも見出せず、疎外感をかこっている存在といってもよいでしょう」(『平野修選集』第二巻15頁)
と述べておられます。あるいは、高柳正裕師は、
「ある哲学者は、人間とは世界に投げ出された『被投的存在』だと言います。またある小説家は『異邦人』だと言います。そうなのです。私たち人間は、気づいていようがいまいが、精神の奥底では無意識に孤児であり、世界や人に出遇えないと悲しんでいる」(真宗大谷派『同朋』2月号21頁)
と述べておられます。
■親鸞聖人が、「十方のよろずの衆生なり」と述べられるとき、そういうふうに自己肯定感を持ち得ず、世界の中に本当の意味での居場所を感じることが出来ずに生きているあらゆる衆生の悲しみを見ておられるように私には感じられるのです。そして、『庶類』・『群萌』と言われるそういう衆生について、親鸞聖人は、「すなわちわれらなり」と書いておられるのです。これは、自己肯定感を持ち得ず、心の中に疎外感を抱いて生きている「十方のよろずの衆生」は、そのまま私自身なのだと述べる言葉です。これは、一体誰がそう言っておられるのでしょうか。親鸞聖人でしょうか。いや勿論そうではありません。法蔵菩薩が、「十方のよろずの衆生」にそのように呼びかけておられるのです。親鸞聖人は、法蔵菩薩のその呼びかけを深い感動をもって聞きながら、このように書いておられるのです。それは、親鸞聖人ご自身が、自分自身を、自己や世界に居場所を見出せずに生きている者だと感じられていたからに外ならないでしょう。
親鸞聖人は、二十九歳の時に、二十年間におよぶ比叡山での修行に完全に行き詰ってしまわれました。『教行信証』「総序」に、
「穢を捨て浄を欣い、行に迷い信に惑い、心昏く識寡なく、悪重く障多きもの」
(真宗大谷派『真宗聖典』149頁)
と書いておられますが、この言葉は、その頃の親鸞聖人の行き詰まった心のあり様をそのまま述べたものではないかと思います。そういうふうに行き場を失っておられた親鸞聖人に、法然上人は、「ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし」と呼びかけられたのです。
■時代も場面も全く違いますが、大分県宇佐市勝福寺坊守の藤谷純子師が、若い頃自身の自我の問題に行き詰ってしまって、自分を仏法に導いてくれた出雲路暁寂先生に、「仏教の勉強をしても言葉がぐるぐる回るだけで、一向にこの身が満たされていきません。もう仏教の勉強はやめます」と申し出た時、先生が、「あなたはもう、本を読んだり理解したりすることでは間に合わないところにいるんだね。お念仏申してみませんか」とおっしゃったと著書の中に書いておられます(真宗大谷派日豊教区出版委員会発行『南無仏の御名なかりせば』10頁~11頁)。その文章が、私の心に強く残っています。出雲路先生がそうおっしゃった言葉に、法然上人が親鸞聖人におっしゃった言葉と同じ質のものを感じるのです
私どもがそれを自己として生きている自我は、自己や他人や自己を取り巻く世界と、本質的に一体化を感じることができないようになっていて、最終的にはどうしても行き詰るようになっているようです。それは、人間の自我の宿命ではないかと思います。そして、それを超える道は、人間の次元にはどこにもないのです。
法然上人や出雲路先生は、そういう自我を生きる私どもに対して、「ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし」と、あるいは、「あなたはもう、本を読んだり理解したりすることでは間に合わないところにいるんだね。お念仏申してみませんか」とおっしゃったのです。ここで述べられている「お念仏申す」とは、人間の行為の次元では全くありません。人間を完全に超えたある大いなるものからの、行き詰まった私どもに対する「念仏申せ」という呼びかけへの、法蔵菩薩の応答なのです。つまり、法蔵菩薩は、私に呼びかけるとともに、また、その呼びかけに応答して、私を破って発起してくる魂でもあるのです。その呼びかけがどういう呼びかけかというと、それが「すなわちわれらなり」という呼びかけなのです。
つまり、自我によって行き詰っている私どもに対して、問題点をあれこれと指摘して、「こうした方がいいよ」とか、「こう改めなさい」というようなことは一切言わず、「行き詰っているあなたは、私そのものです」「私は、行き詰っているあなたを私そのものとします」「私は、それ以外のものではありません」「私は、そのあなたの所に居ます」「今までも久遠劫来そのあなたの所にずっと居ました。これからも永遠にそのあなたの所に居続けます」―そういう法蔵菩薩の呼びかけ、それが「すなわちわれらなり」という呼びかけではないかと思います。その呼びかけは、法然上人が呼びかけておられるのではなく、法然上人も聞かれた法蔵菩薩の呼びかけなのです。親鸞聖人は、法然上人を通して、行き場を失っている自分に向ってそう呼びかける法蔵菩薩の永遠の呼び声を聞かれて、心の底から感動されたに違いありません。その呼び声によって、始めて、今までどうしても自己肯定感の持ち得なかった自分自身に、そのまま帰ることが出来たのです。
■では、そのような呼びかけを人類の中で最初に聞かれた方は誰でしょうか。それが釈尊です。『無量寿経』「下巻」の最初の所で釈尊は、「諸有衆生、聞其名号」と説いておられます。「諸有衆生」とは、様々な怯えを抱いて迷っている衆生ということです。これは釈尊ご自身のことでしょう。悟った釈尊が、未だ悟らずに迷っている他の衆生のことを言われた言葉ではありません。他の仏者はともかく、少なくとも親鸞聖人においてはそうだったのです。親鸞聖人においては、『無量寿経』を説かれる釈尊と、他の八万四千の経典を説かれる釈尊とでは、同じ釈尊でも釈尊観が全く違うのです。その「諸有衆生」としての釈尊が、「すなわちわれらなり」という法蔵菩薩の呼び声を聞かれたのです。それが「聞其名号」という言葉です。
■では、釈尊は、その法蔵菩薩の呼び声を聞かれてどうなられたのでしょうか。それを述べているのが、次に続く「信心歓喜乃至一念」という言葉です。この言葉の主語は誰でしょうか。「信心歓喜乃至一念」と感動するのは誰が感動するのでしょうか。それは、今までの私ではありません。今まで「私が、私が」と言っていた、その私の手の届かない深い所に、久遠の昔からずっと埋もれ続けていた法蔵菩薩の魂が、呼びかけに呼び覚まされて、今までの私を押し開いて生まれてきて、「信心歓喜乃至一念」と感動するのです。
■藤谷純子師は、そのときの様子を著書の中で次のように書いておられます。
「『南無阿弥陀仏の御名を称えるところから、新しい生活が始まりますよ』と先生(信国淳師)がおっしゃったように、その言葉から呼び出されるように、やがて私の心身深くより念仏申さんとする生活が始まったのでした。お念仏申すには、法然上人の『一枚起請文』には、『一文不知の愚どんの身になして、尼入道の無ちのともがらに同じくして、ちしゃのふるまいをせずして、只一こうに念仏すべし』とあります。もとより愚鈍の身、無知のわが身に帰って「ナンマンダブツ」と念仏申す身のよろこび。それは、久遠劫来はじめて合掌し念仏するわが身に、私が出遇ったような出来事でした。今まで『私が、私が』と言ってきた私から始まったのでない、むしろその私が、合掌して念仏申す身に従って聞法させていただこうという生活がひらかれてきたのでした。そしてそれは、『念仏申してこの身を生きていこう』とはじめて自分が一つに決まったということでもあります。」
(『南無仏の御名なかりせば』25頁~27頁)
何という深い喜びの伝わってくる文章でしょうか。
ここには、「すなわちわれらなり」という法蔵菩薩の呼びかけを聞いて「信心歓喜乃至一念」したら、いったいどういう生活が私どもの上に開かれてくるのかということについてもすでに述べられています。
■『無量寿経』では、それをあらわす言葉が、「信心歓喜乃至一念」の次に続く「至心回向 願生彼国 即得往生 住不退転」という言葉です。
「至心」とは、法蔵魂、すなわち法蔵菩薩の願心のことでしょう。その魂が、今までの私を押し開いて私の上に顔を出してくる。それを「至心回向」というのでしょう。そして、「願生彼国」とは、そういうふうに新しく私の上に顔を出してきた法蔵菩薩の願心を生きる生活が始まることをいうのでしょう。
法蔵菩薩の願心とは、親鸞聖人が『教行信証』の終りに「無辺の生死海を尽さん」(『真宗聖典』401頁)と願って歩み出された道、すなわち、法蔵菩薩が、尽きることのない衆生の迷いの海を「すなわちわれらなり」とされた如く、自分もそういう法蔵菩薩の命をわが命として歩んでいこうと立ち上る道です。具体的には、念仏もうしながら自他の煩悩や宿業に向き合っていくという道ではないかと思います。衆生の迷いは尽きることがありませんので、この道も終わることがありません。
そして、そういう道に立ったことを「即得往生」というのでしょう。その道は、肉体の死によっては終わらない道です。清沢満之先生が、「生のみがわれらにあらず、死もまたわれらなり。われらは生死を並有するものなり」と言われたように、個々の肉体の死を突破し、法蔵菩薩の本願をわが命として生きていく道です。 そして「住不退転」とは、「すなわちわれらなり」と法蔵菩薩に呼ばれているわが身に一度目覚めたら、その後、たとえ呼び声を忘れてわが身を見失うことがあっても、ずっと見失ったままで終るということはなく、必ずまた呼び声に呼びもどされ、呼ばれているわが身に立ち返って再出発することが出来るということではないかと思います。その歩みが止まることはもはやないということでしょう。先に引用した藤谷純子師の文章が、そういう生活を実感に即してよく語ってくださっているように思います。すなわち、念仏申しながら、聞法しながら、煩悩の身、宿業の身に帰っていくという道、そういう生活が開かれてくるということです。
■このように、「すなわちわれらなり」という言葉は、『無量寿経』「下巻」に出てくる「聞其名号」の「名号」、すなわち法蔵菩薩の呼び声に内容的に相当するものだと思います。自分自身の自我の闇に行き詰って、生きる意欲さえ見失っていた者が、法蔵菩薩のこの呼び声が聞こえてきたことによって、もはや自我の声に耳を傾けることなく、ただこの本願の呼び声一つを聞きつつ生きていこうと生れ変る。そこに、「『念仏申してこの身を生きていこう』とはじめて自分が一つに決まった」と藤谷純子師が書いておられるように、今までどうしても受け入れることができなかった自身の宿業の身に帰って生きていく道が開かれる。そういう往生の道が開かれるのです。
これは、人間の次元の一切に行き詰った者が、人間の次元を超えた名号という呼び声に触れて新しく生まれ変わるという道です。これは、単なる教義の問題ではありません。宗教の違いをも突破した道です。最近私は、キリスト教の牧師小笠原亮一師の回心体験を読んでそのことを強く感じる経験がありました。生きる意欲をすっかり失って自殺未遂にまで至った小笠原師が、三度まで裏切ったペテロに注がれるイエスの眼差しに触れ、以後イエスの自分に注がれる眼差しのみをいただきつつ生きていこうと蘇った。その転機について語っている文章に触れて大きな光を感じたのです。そこで、次のブログ(No8)では、そのことについて書いてみたいと思います。