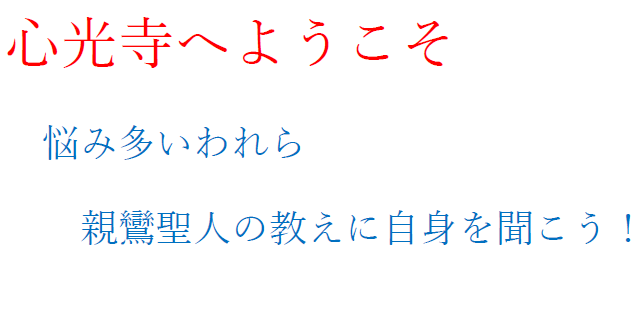No4-一人ひとりに法蔵菩薩がついておられる
- bunryu
- 2020年1月18日
奥さんを亡くされたOさんの悲しみ
■2020年1月2日。この日から、一軒々々正月のお参りを始める。昨年の盆過ぎに奥さんを亡くされたOさん宅にもお参りした。奥さんのN子さんは、66歳だった。亡くなられるまでの二十数年間というもの、体中の痛みに苦しめられ、ペインクリニックに通院しておられた。最期は、骨と皮のようにやせ細って、枯れ木のようになって、亡くなっていかれた。療養中は、薬代が、家計に相当な負担になっていたようだ。Oさんは、勤めていた会社が倒産し、湯布院の旅館で夜勤の仕事を続け、家計を支えておられた。N子さんは、そういう体なので、思うように家事は出来なかった。二人は再婚同士で、N子さんは、元気な頃は看護師だった。Oさんは、冗談交じりに、「看護師と結婚すれば経済的に助かると思って一緒になったところが、とんでもない厄病神と結婚してしもうた」と、表向きには、よくぼやいておられた。しかし、ある時、Oさんの不在時にお参りに伺った折、N子さんが、私にこう話してくれたことがある。
「この間、Tさん(Oさんの下の名前)が、『これは、わしの〈のさり〉じゃ』と言った。それで、私がTさんに、『Tさん、それはどういう意味かえ』と聞いたら、『お前を看ることが、わしの仕事じゃという意味じゃ』と答えた」と。
これには、私も感動した。私は、N子さんに言った。「それは、凄い言葉ですね。自分の仕事として、お前の面倒をみていこうと思うておる。だから、安心してくれと、そういう覚悟を、そんな言葉で言ってくれたんですね。Tさんは、優しいね」と。そしたら、N子さんは、「そうです!」と、しみじみ頷かれた。
私がお参りに行ったとき、N子さんは、いつも茶の間の窓辺に置いたベッドの上に横になっておられた。しかし、この間、正月のお参り行くと、そのベッドは撤去され、茶の間は広々としていた。いつもそこで横になっておられたN子さんが居られないのは寂しかった。
「Oさん、寂しくなりましたね」私がそう言うと、「そうです。今まで、薬代がかさんで困ると周りにもよくぼやいていたが、亡くなってみると、薬代を稼がねばという気持ちが働くエネルギーになっていたんですね。その励みの元が、もう無くなってしもうた。夜勤の仕事が終わって家に帰っても、いつもN子が寝ていたベッドが無くなってしもうて、寂しくてやりきれません」Oさんは、そう絞り出すように言われた。頬には、涙が流れていた。
「法蔵菩薩は阿頼耶識なり」
■Oさん宅を辞し、車を発進させつつ、次のようなことを思っていた。
◇一人ひとりに、法蔵菩薩がついておられる。Oさんの中にも、亡くなっていかれたN子さんの中にも、そして、この私の中にも。
◇その法蔵菩薩は、その人の全宿業に不二――(離れずあたかも 一つの存在のようになること)――となって、その宿業の全責任を負うて、歩んでいかれる。
◇その法蔵菩薩は、善し悪しを一切言わない。その人が、どんなに転落しようが、どんなに 罪を犯そうが、黙々としてその人に従い続け、その人の全存在を支え続けていかれる。
◇その法蔵菩薩は、単なる神話的存在ではない。われらの無意識の底、深層意識の最深部に、阿頼耶識として働き続けておられる。そういう働きとして実在される。
◇そのことを、曽我量深先生は、「法蔵菩薩は阿頼耶識なり」と言われた。
◇この阿頼耶識は、われらの無始以来の全経験を収める無尽蔵の蔵だ。この蔵に収められている経験の種子が、因となり、縁にふれて、果として現行したのが、現在のわれらの存在なのだ。
◇従って、阿頼耶識は、われらの先験的自己だ。
◇われらの存在の最深部に、このような無意識の層があることを突き止められた、瑜伽の行者、唯識学派の学僧たちの人間洞察の深さと鋭さには、心底驚嘆する。
三人の人を殺めた男の話
■そんな思いが過ぎりつつある時、私にとって忘れられないある事件の話を、再び思い起こした。それは、藤原正遠師が、かつて『あや雲の流るる如く』という随想集の中に書いておられた次のような話だ。
◇ 「余程前の話になるが、朝鮮の人で日本人の女と内縁関係の男があったそうだ。所がどういう理由か知らぬが、ともかく女が家を飛び出して、富山の山奥の自分の家に逃げ帰った。男はその後を追って、その女の家を訪ねた。しかしその女は再びその男の所に帰ろうといわぬし、又女の親達がその男をさんざん罵倒したのであろう。その夜その男はその女の家のものを、たしかその女とその両親を殺したのである。そしてやがてその男は捕まったのであるが、あとで警察の人の尋問に対して答えた言葉がある。 『お前はその山奥から五里の道を町へ下りてくる時、どうして来たか。』 『ハイ。五里の道を走りながらお念仏をただ夢中で称えながら、走って来ました。』と。
この朝鮮の人は、向うで生まれられたか、こちらで生まれられたか知らぬが、ともかくどこかでお念仏の謂れが耳に入っていたのであろう。
この話には、とやかくの議論もあろうが、私には胸を打つ話として、現在も 新しく耳の底に残っている次第である。」 (『あや雲のながるる如く』上・19頁)
人間業を超えた問答
■私がこの文章を読んだのは、もう16、17年位も前のことだが、私には、この事件の話が、あまりにも衝撃的で、深く心に残っている。私に衝撃を与えたのは、事件そのものではない。事件そのものであれば、そういう事件は、今日の時世では、さほど珍しくはない。私に衝撃を与えたのは、その男が捕まった後、警察官が、「お前はその山奥から五里の道を町へ下りてくる時、どうして来たか」と聞いたことと、それに対して男が、「ハイ。五里の道を走りながらお念仏をただ夢中で称えながら、走ってきました」と答えたことである。、私には、この問答は、まったく人間業を超えているように感じられた。その問答に衝撃を受けたのである。
このことについて、私は、かつて『心光寺定例聞法会便り』(第1期)の中に書いたことがある。それは、次のような文章だ。
◇「…私は、ふとこの一節を目にして以来、そこに書かれている情景が心に残り、何かにつけてしばしば思い起します。 いかなる宿業か、その男は三人の人を殺めてしまったのです。この恐ろしい惨劇の後、修羅と化した心を抱いて五里の山道を走り下る時、その男は一体いかなる心持ちであったのか。人間の奥底に流れる真実に少しでも関心を注ぐ人ならば、これは何人もとうてい聞き流すことのできない重要な問題ではないかと思います。警察の人もそんな大事なことをよくぞ聞いてくださったものだと感謝いたします。 どのような感情も言葉も説明も、このような宿業の前には言葉を失ってしまいます。ただ事実だけが、一切の説明を拒んでそこに横たわっています。このような事実の重さに直面した時、人は一体どのような心持になるものでしょうか。おそらく、その時その男の心持は、白紙に近いものだったのではないかと思います。どのような人生観も、主義も、思想も、信仰も、その事実の前には、貧弱なものに映るばかりです。
その時その男はどう答えたか。それが次のような言葉だったのです。
『ハイ。五里の道を走りながらお念仏をただ夢中で称えながら走って来ました』
私はこの言葉が創作上のものでなく、実際に重大な過ちを犯してしまった人の口から出た言葉であるだけに、深く心を打たれるのです。そこに、人間の深い真実が現れていることを感じます。このような宿業の重さに釣り合うほどの思想も、信仰も、とうてい人間の中には見出すことができません。ただ念仏のみが、是非善悪を超えて、その事実を、事実のままに受け止める世界であることを感じるのです」(平成15年1月号『心光寺からの便り』より)
宿業の重さに釣り合うもの
■このような宿業の重さに釣り合うものは、人間のいかなる思想にも信仰の中にも、見出すことはできない。ただ念仏のみが、是非善悪を超えて、事実を、事実のままに受け止める世界なのだ。その時、私は、確かにそう感じた。そして、今は、それこそが、称名念仏の「称」の意味に他ならなかったと気づかせていただいている。
親鸞聖人は、「称名」の「称」という字について、『教行信証』「行巻」に、「軽重を知る也」「銓(はかり)也」という註をほどこしておられる。『一念多念文意』の中にも、「称は、はかりというこころなり。はかりというは、もののほどをさだむることなり」と書いておられる。これは、非常に重大な注釈であると思う。
この注釈によって知らされることは、まず第一に、称名念仏の「称」は、発音ではないということである。その点が、題目を唱えるという場合の「唱」とはまったく異なる。では、発音ではなければ、いったい何なのか。それについて、親鸞聖人は、「南無阿弥陀仏」と念仏を称えることは、「ものの軽重を知ること」、「はかりのこと」だと言われる。ここで重要になるのは、「もの」とは、いったい何を指すのかということである。そのことについては、親鸞聖人は何もふれておられない。しかし、『教行信証』「信巻」の終りの方に、中国の曇鸞が『浄土論註』の中で述べている、いわゆる八番問答と呼ばれる文章を引用しておられる。その八番問答の第六番目の問答の中に、次のような文章があるのだ。
◇ 「『業道経』に言わく、『業道は称のごとし、重き者先づ牽く」と。『観無量寿経』に言うがごとし。『人ありて五逆・十悪を造り、もろもろの不善を具せらん。悪道に堕して多劫を径歴して無量の苦を受くべし。命終の時に臨みて、善知識教えて南無阿弥陀仏を称せしむるに遇わん。かくのごとき心を至して声をして絶えざらしめて、十念を具足すれば、すなわち安楽浄土に往生することを得て、すなわち大乗正定の聚に入りて、畢竟じて不退ならん、三途のもろもろの苦と永く隔つ』」
親鸞聖人が、称名念仏の「称」について、「ものの軽重を知ること」、「はかりのこと」だというふうに注釈された時、おそらく曇鸞のこの文章が念頭にあったのではなかろうか。この文章の文脈から考えると、「もの」とは、「業道」、それも「五逆・十悪を造り、もろもろの不善を具せらん」悪業のことを指している。
ところで、今日では、「はかり」と言えば、皿の上に物を載せて計る「上皿計り」が一般的だ。しかし、親鸞聖人の時代には、そのような「上皿計り」は存在しない。「はかり」といえば、もっぱら「天秤計り」のことだ。「天秤計り」とは、天秤棒の真中を支えて支点とし、天秤棒の片方の端に、質量を測定しようとする物体を吊るし、もう片方の端に、あらかじめ重さの分っている分銅をぶら下げて、釣り合った時の分銅の重さによって、物体の重さを測定する計量器具のことである。
その天秤棒の一方の端に、上記に述べた「五逆・十悪を造り、もろもろの不善を具せらん」悪業をぶら下げた時、もう一方の端にぶら下げるのに、それに釣り合うものが、いったい、この世の中に存在するものであろうか。否!である。そのような悪業と釣り合うものは、人間世界の中には、どこにも存在しない。ただ「南無阿弥陀仏」と称えることのみが、そのような悪業と、ぴたりと釣り合って、その悪業を丸ごと支えることができるものなのだ。親鸞聖人は、称名念仏の「称」を「はかり」と注釈されることによって、このことを言わんとされたのだと思う。
『観経』に説かれる臨終の悪人の救い
■ところで、曇鸞の上記の文章は、『観無量寿経』の経文の一節に基づいて書かれたものだ。その経文とは、臨終の悪人が、善知識の勧めによって南無阿弥陀仏と十遍称えて往生したと説かれている経文である。このことについて、以前、前掲の『心光寺定例聞法会便り』(第1期)の中に書いたことがある。それは、次のような文章だ。
◇「『観無量寿経』では、浄土往生のために実践すべき具体的な行を説くにあたって、人間の資質を九段階に分け、それぞれの段階に応じて実践行を説き分けています。どの程度の実践行に耐えうるかは人によって大きく異なるからです。その九段階の機類とは、まず人間の機類を上品・中品・下品の三段階に分け、それぞれの段階を、更に上生・中生・下生の三段階に更に分けて、全部で九段階としています。その一番上の機類は上品上生と呼ばれ、次は上品中生と呼ばれ、そして一番下の機類は下品下生と呼ばれています。 さてこの一番下の下品下生の人とは一体どのような人のことをいうのでしょうか。経典によれば、下品下生の人の一生涯は、ただ五逆罪――(人倫や仏道に逆らう五種の極悪罪で、犯せば地獄に堕ちるとされる)――と、十悪業――(①殺生②盗み③不倫④うそをつく⑤不誠実で内容のない言葉を並べる⑥人の傷つくことを言う⑦陰口を言う⑧際限のない欲望⑨怒り⑩自己の姿に暗く智恵がないこと)――を積み重ねることにのみ費やされて、良いことは何もしてこなかった。そのような悪人が今臨終の時を迎えている。命終ればこの人は、自らの悪業のために悪道に堕ちて長い間苦を受けねばならないことは目に見えている。このような切羽詰まった状況にあると説かれています。
『観無量寿経』では、この絶体絶命の人に対して、一体どのような教えが説かれているのでしょうか。 まず善知識(よき師よき友)が妙なる教えを説いてその人の心を落ち着かせ、その上で「心の中に仏を念じなさい」と勧めます。ところがその人は、仏を念じようとするけれども、病苦にせめられてどうしても仏を念ずることができません。そこで泣く泣く、「私にはできません」と訴えます。 実際、このような臨終を目前にした悪人に対して、一体どのような実践行を説くことができましょうか。《こうすればこう良くなる》というような向上を目指す道徳や修行の一切が全く間に合わない状態にあるのですから。
そこで善知識は、 「わかった。汝もし仏を念ずる余裕がないのであれば、声に出して仏様の御名を称えなさい。私が今から実際にして見せるから、私についていっしょに仏様の御名を称えよう」 こう言って、合掌して南無阿弥陀仏と称えました。そこで、その男も、善知識にならって、合掌して南無阿弥陀仏と称えました。このようにして十遍南無阿弥陀仏と称えた後、その人は息絶えました。しかしそうして仏様の御名を称えたことによって、その人は、自らの一生涯を深く懺悔し、また深く満足して、命終の後、即座に浄土に生まれることができたのです。このように『観無量寿経』には説かれています(趣意)。これが下品下生の臨終の悪人についての経典の描写です。
臨終の悪人とは、これから努力していけば良くなるというような理想主義的な教えが一切間に合わない所に追い込まれている人の姿を象徴しています。曇鸞大師も善導大師も法然上人も親鸞聖人も、このような臨終の悪人の上に、宿業の身を生きる自己の真実の姿を見られたのです。そして善知識の勧められるままに、ただ念仏申す人となられたのです」(平成15年1月号『心光寺からの便り』―一部訂正―より)
排斥の的となった称名念仏の経説
■この『観無量寿経』に説かれている所の悪人の十称念仏による往生の経説は、浄土教において、きわめて重要な仏説として伝承されてきた。親鸞聖人は、『歎異抄』第二章において、「弥陀の本願まことにおわしまさば、釈尊の説教、虚言なるべからず。仏説まことにおわしまさば、善導の御釈、虚言したまうべからず。善導の御釈まことならば、法然のおおせそらごとならんや。法然のおおせまことならば、親鸞がもうすむね、またもって、むなしかるべからずそうろうか」と、自身にまで伝わってきた念仏の信心の伝統を述べておられる。ここで述べられている「釈尊の説教」「仏説」こそは、『観無量寿経』に説かれる所の臨終の悪人の称える称名念仏についての経説に他ならないのだ。
しかし、一生造悪の悪人が、死ぬ間際に南無阿弥陀仏と十遍称えて、それで往生できるなどという経説は、常識では、とうてい信じることはできないだろう。その為、この称名念仏の教えは、長い浄土教の歴史の中で、つねに排斥の的にされ続けてきた。歴史上有名な論難では、中国の隋、唐時代に、摂論宗の徒が、『観経』に説く所の下品下生の悪人の十称念仏による往生説は、釈尊が方便の為に説いたものである。実際は、往生できるといっても、遠い未来のことに過ぎない。しかし、そう言ってしまえば、始めから往生を願う心も放棄してしまうので、釈尊が、悪人に対しても、わずかでも仏道に縁を持たせようとして、方便の為に、念仏を称えれば命終の後すぐに往生できると説いたのだ、と主張した論難がある。
その譬えが面白い。たとえば、十称の念仏で往生できると説いたのは、一円のお金でも、気が遠くなる程長い間貯金していけば、いつの日にか遠い未来には億単位の大金になる。それを、貯蓄を励まさんとする方便の意図から、すぐに大金を得ることができると説いたようなものだと。この説は、大いに説得力を持ったようで、それまでかなりの勢力を持っていた称名念仏の教えが、この説によって、瞬く間に衰退していったそうだ。
なぜその説がそれほど説得力をもったのかといえば、その説が、正に常識に合致するものだったからである。我々の常識は、根っからの努力主義なのだ。長い間の厳しい仏道修行に耐えた結果往生できると説かれれば、それは尤なことだと納得するが、一生造悪の悪人が、臨終に南無阿弥陀仏と十遍称えて、それで往生できると説かれれば、そんな馬鹿な話はあり得ないと一笑に付してしまうのだ。
宿業の身に対して人間は全く無力
だが、臨終の悪人というのは、そういう特殊な状況にある人のことだけを取り上げて言っているのではない。およそ生死無常の身、煩悩熾盛の宿業の身を逃れられない所のわれら人間の身の事実の真相を、そういう特殊な事例によって表しているだけなのだ。そのような生死無常の身、煩悩熾盛の宿業の身に釣り合うようなもの、言いかえれば、釣り合って支えられるようなものは、およそ人間の中にはないのだ。たとえ長い間の仏道修行を積み重ねたところで、生死の身、宿業の身の前には、たちまち吹き飛んでしまう。それは、ちょうど、富士山を人間の努力によって動かそうとしているようなものだ。十声の呪文は勿論のことだが、たとえ長い間の修行によっても、富士山はびくともしない。それと同じように、生死の身、宿業の身も、人間のいかなる努力によっても、びくともしないのだ。およそ人間の中には、いかなる修行も努力も、生死の身、宿業の身を前にして、間に合うものは、何一つないのだ。
無論、十声の「南無阿弥陀仏」の発音でも、びくともしない。それで、親鸞聖人は、釈尊が『観経』の中に説かれた所の称名念仏の「称」とは、発音でない、「はかり」のことだと注釈されたのだ。
「はかり」とは、前述したように、生死の身、宿業の身に釣り合うものは、人間世界の中にはない。宿業の身に釣り合うものは、宿業の身それ自体のみだ。「南無阿弥陀仏」の声は、人間世界から出てくるものではなくて、宿業の身それ自体から涌き出た所の声だ。宿業の身から涌き出て、宿業の身と一つになって、どんなことになろうとも、決して捨てず、どこまでも運命を共にして歩み続けるという宿業の身の魂なのだ。「南無阿弥陀仏」は、その宿業の身の魂の叫び声だ。すなわち、法蔵菩薩の産声なのだ。親鸞聖人が、「称」を「はかりなり」と注釈された元には、そのような直覚があったに違いないと私は思っている。
■このブログの冒頭に、「いかなる人にも、どんな生涯を送った人にも、一人ひとりに法蔵菩薩がついておられる」というふうに書いた。このことは、いかなる人にも、それに釣り合う「南無阿弥陀仏」の呼び声が与えられているということと同じことなのだ。
二十数年間もの間、全身の痛みと闘い続けて、枯れ木のように痩せ細って亡くなっていかれたN子さんにも、妻を亡くして呆然ととしておられるOさんにも、ちゃんと法蔵菩薩が、離れずに、ついておられる。この私にも、法蔵菩薩がちゃんとついてくださっておられる。あるいは、こんなことを書くと周囲から袋叩きにあいそうだが、今新聞をにぎわしている、相模原知的障害者施設殺傷事件の植松聖被告にも、法蔵菩薩がちゃんとついておられる。 (註・植松聖の犯罪を肯定しているということとは違う。そういう善し悪しの価値判断以前の、あらゆるいのちの根底をささえている魂の構造、働きのことを言っている)
要するに、どんな人にも、一人ひとりに法蔵菩薩がついておられて、その人がたどる無始の過去から未来際に至るまでの、その人の全宿業の歩みに、善し悪しを言わずただ黙って従い続け、運命を共にされるのだ。その法蔵菩薩の声を、宿業の身と釣り合う「南無阿弥陀仏」の声というのである。
宿業の身を呼ぶ声を、ただ聞かせていただく
■私は、以前、蓬茨祖運師が書かれた『春逝く人』をブログに取り上げた(『法蔵菩薩は永遠の青年』)。死を目前にした青年が、どうしても死にたくないのに死んでいかねばならぬという、人間の力ではいかんとも為し難い、厳しい生死の身の現実に直面している。そういう状況の中で、念仏は、人間の力ではいかんとも為し難い生死の身から涌いて出た法蔵菩薩の呼び声であることを覚って、ただ念仏称える人となって死んでいかれたことを書いている。この話も、親鸞聖人が、「南無阿弥陀仏」と称えることは、「はかりというこころなり。はかりというは、もののほどをさだむることなり」(『一念多念文意』)と注釈されたことと、ぴたりと一致する。
要するに、われらの一挙手一投足は、すべて宿業にもよおされて為さぬものは何一つないのであって、そこに人間の如何なる思慮分別心も介在する余地はないのだ。そういう人間の宿業の身の事実と、ぴたりと釣り合うものは、人間世界の中には、どこにも存在しないのだ。それと釣り合うものは、その宿業の身それ自体から涌き出た所の南無阿弥陀仏の呼び声のみなのだ。
親鸞聖人が、「親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり」というふうに、「別の子細なきなり」と言われたのは、そのことをおっしゃっているのだ。また、師の大石法夫先生が、「教えは人間の思想や信念ではありません。人間の思想だったら、人の思想と対立します。否定、肯定の世界になります。ご本願は、人間の心の根底を突き破って、火山の噴流のごとくわき出てくださるものです」(書信第87信)と書いておられるのも、そのことをおしゃっておられるのだ。
念仏は、人間の思慮分別心を一切経由しない。従って、いかなる人にも平等なのだ。頭がいいとか悪いとか、ものをよく知っているとかいないとか、行いがいいとか悪いとか…等々、そのような人間の属性に一切影響されないのだ。
■私も、もうすぐ古稀を迎える。物忘れも頻繁となり、理解力も衰えていくばかりだ。これから年とともに弱っていき、やがて死を迎える。そういう私にとって、人間の思慮分別心を一切経由せず、われらの宿業の身とぴたりと釣り合って涌き出る南無阿弥陀仏の呼び声を、ただ聞かせていただく。この簡明直截な教えの有難さを、最近、いよいよ感じるのである。