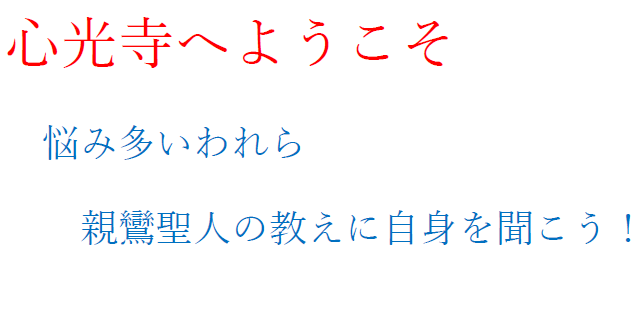No2-「どのように生きていったらよいのでしょうか」
- bunryu
- 2019年11月23日
「どのように生きていったらよいのでしょうか」
◆師の大石法夫先生は、昭和18年12月、京都大学を繰り上げ卒業となり、海軍に入隊された。入隊後、水中特攻兵器「回天」の搭乗員となり、山口県の光基地で、出撃に備えての訓練に明け暮れる日々を過ごされた。出撃命令が下りれば、魚雷ごと敵艦に激突しなければならない。当然死を覚悟しておられたが、終戦によって死をまぬかれ、再び大学にもどられて、1年間、後輩たちにまじって法律の勉強を続けられた。やがて、就職も決まり、結婚も決まった。しかし、内面は、生きる方向を見失い、不安を抱えておられた。そんな時に、師の藤解照海師に出遇われたのである。師に出遇われて、最初にお尋ねされたことの一つが、「どのように生きていったらよいのでしょうか」だったと、著書『生まれてよかったですか』の中に書いておられる。
ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし
◆「どのように生きて行ったらよいのでしょうか」――おそらく親鸞聖人も、この問い一つを抱えて20年間比叡山で修業されたにちがいない。しか、比叡山ではついにその解決は得られなかった。
聖人の妻恵信尼が書かれた『恵信尼消息』によれば、行き詰られた聖人は、29歳の時山を下りられて、聖徳太子の開基と伝えられる六角堂に百日間の参籠を開始されたという。そして、95日目の未明、六角堂の本尊、救世観音菩薩の夢告を受け、吉水の法然上人の下へと走られて、六角堂に百日籠られたのと同じく、また百日間の聞法を開始されたのである。
ところが、法然上人は、「どのように生きていったらよいのでしょうか」という問いに対して、つねに「ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし」と、このこと一つを繰り返しおっしゃられるのみであったという。
念仏は、生きる方法の提示ではない
◆これは、「どのように生きたらよいのでしょうか」と生きる方法を探し求めている人に対して、「念仏をもうしなさい」という一つの方法を提示する言葉と受け止めるのが普通であろう。事実、法然聖人の他のお弟子方のほとんどは、そう受け取られた。そして、念仏の行に走られた。だが、親鸞聖人には、そうは思えなかったのではなかろうか。もしそうなら、百日間も聞法に通い続ける必要はなかったであろうから。
おそらく聖人は、法然上人のこの言葉に、「どのように生きたらよいのでしょうか」と、生きる方法を探し求めている自分とは、全く次元の異なる未知の領域からの響きを感じられたのではなかろうか。そこに、何か魂に訴えかけてくるような響きを感じられたのではなかろうか。しかし、それが一体何であるのか、それがわからない。だが、何としてもその本源に触れたい。その一心で、「又、六角堂に百日こもらせ給いて候いけるように、又,百か日、降るにも照るにも、いかなる大事にも、参りてありしに」と、妻の恵信尼が、後に『恵信尼消息』に書かれたように、ただひたすら法然上人の下に通い続けられたのにちがいない。
そして、ついに、人間の領域を超えたその呼び声が、聖人の魂に届いたときの様子を、恵信尼は次のように表現している。
「ただ、後世の事は、善き人にも悪しきにも、同じように、生死出ずべきみちをば、ただ一筋に仰せられ候いしをうけ給りさだめて候いしかば」 (『恵信尼消息』)
「後世の事」
◆ここに、「後世の事」という言葉がある。「後世」とは、「今生」に対する言葉で、人間の領域、生まれてから死ぬまでの人間の時間世界を超えた、阿弥陀仏の時間世界の領域を、そのような言葉で表現しているのであろう。
大石先生もおっしゃっておられたが、私ども一人一人の人生には、人間の力ではどうすることもできない力がはたらいている。その意味で、人間は有限であり、無力である。そういう私どもにとって、いったい本当の帰り場所はどこにあるのか。「どのように生きたらよいのでしょうか」という、生きる方法を求める問いの根底には、実は、有限な人間の時間世界を超えた永遠の時間世界に触れたい、そういう世界に帰って安心したいという欲求がはたらいているのではなかろうか。
「後世の事」とは、そのような、万人の底に流れている深い宗教的欲求を表す言葉ではなかろうか。
「信じる」「念仏を称える」とは
◆大石先生が、「本願が信じられるということは、仏さまの方が成就して待っていてくださったその願いが、届いてくださったということです」と書いておられるように、「信じる」とか「念仏を称える」ということは、私どもの側の心的行為の出来事ではなく、有限な人間の時間世界を超えた阿弥陀仏の大悲の世界が、生死の迷いを出ることができない私どもを丸ごと受け止めて、「念仏もうせ」と呼びかけてくる、その呼び声が私どもに届いた出来事をいうのである。その呼び声が届くとき、始めてわれらは、生死の迷いをどうしても出ることが出来ないわが身に帰り、そこに安住することが出来るのである。
人生は、人間の力ではどうすることもできない
◆そんなことを思いながら、今朝、、ごみ置き場へごみ出しに行き、帰りに、心光寺の掲示板に掲げている大石先生の言葉が、改めて目に留まり、心に響いてきた。それは、次のような言葉である。
「人生」
「人生には、人間の力ではどうすることもできない力が働いているのです。お一人お一人が、『念仏して救われていく』ほかに進むべき道はありません」
これが、掲示板の言葉である。先生がこう述べておられるように、私どもの人生には、人間の力ではどうすることもできない力が働いていると言わざるを得ない。人生の出来事のどれ一つをとっても、あるいは、日々一瞬も休むことなく湧いてはわれらを悩ませ続ける煩悩のどんなささいな一思いをとっても、そうでないものは何一つない。清沢満之先生が、「現前一念における心の起滅、亦自在なるものにあらず」と述べておられる通りである。
そういう私どもにとって、
「そのお前のままで、私の所に来い。私は、そのお前を待っている。そして、そのお前を、私は永遠に生きていく。そのお前を、どんなことがあっても決して捨てはしない。だから、もう心配しなくていい」
この阿弥陀仏の呼び声のみが、どうにもならないものを抱えて生きねばならない私どもの最終的な帰り場所なのである。安住の世界なのである。その阿弥陀仏の呼び声が、念仏なのだ。
何を持って来ても埋められないものを抱えた身
◆佐野明弘師の次の言葉も改めて憶念される。
「私たちは、何を持って来ても埋められないものを抱えている。そこが、念仏をいただく場所だ」
「何を持って来ても埋められないものを抱えている」身。これは、どんな方法も間に合わぬ身ということだ。親鸞聖人は、それを「いずれの行もおよびがたき身」と言われた。われらは、そういう身から目をそむけ、そういう身から逃れる方法ばかりを一生懸命に探し求めている。「どう生きたらよいのでしょうか」という問いも、意識的には、そういう身を逃れる方法を探し求める問いなのだ(無意識的には、もっと深い要求が働いていると思うが)。
ところが、阿弥陀仏は、われらが目をそむけているところの「何を持って来ても埋められないものを抱えている身」をこそ呼んでおられるのである。われらは、その呼び声であるところの念仏の声が聞こえてきた時、始めて、久遠劫来自分が目をそむけてきたわが身、すなわち、「何を持って来ても埋められないものを抱えている身」に、安んじて帰ることができるのである。自分からは決して帰ることはできないのだ。
そういう念仏の声が聞こえてきた時から、われらの前には、念仏もうしつつ、「何を持って来ても埋められないものを抱えている身」に帰り、その身に帰って、また念仏もうし、こうして、念仏もうせばもうすほど、いよいよその身に帰っていく、そういう一本道が開かれてくるのである。それが、往生の一本道である。
内観の念仏
◆実はこれは、在家の念仏詩人であった榎本栄一師が、松原致遠師の著書『わが名を称えよ』に序文を書いておられる。その序文の一節が私の心に深く残っていて、その一節を念じながら書いたものである。その一節とは、次のような一文である。
「その折の私はまだ念仏さえ称えておりませんでしたけれど、それから何十年もたって、松原先生もお亡くなりになり、他に縁のあった先生方もお亡くなりになった――その頃から、思いもかけず私のなかからひとりでに念仏が生まれるようになってまいりました。そして、念仏申せば自分が見える、自分が見えるということは自分の煩悩が見えるということが、おぼろげに感じられて目の前に一本の細い道が開けてきました。それが先生のおっしゃていた智慧の念仏、内観の念仏でありました。
内観とは自分の煩悩が照らされることです。自分の煩悩が照らされて、その煩悩を阿弥陀様にお任せして、流れるままにひっつかず手放しているのが往生浄土の道であるというようにお説き下されたのは、松原致遠先生しか私は知りません。念仏申せば内観深まり、内観深まればいよいよ念仏申される、申しながら深まりながら申しながらという――そこが今回のこの著作を拝見いたしましても、ただ一つの眼目に違いありません。そしてそれが私を生かし、今日を新たに歩ませて下されるもとのもとの力になっているのであります」 (松原致遠著『わが名を称えよ』の榎本栄一師の序文より)
親鸞聖人の前に開かれてきた道
◆ここに、念仏の呼び声によって、始めて、今まで向き合うことのできなかったわが煩悩に、静かに向き合うことのできる道が開かれてきた喜びがつづられていて、私の心を打つのである。
そのような道が、法然上人の下へと通い続けた百日間の聞法を通して、二十九歳の時、親鸞聖人の前に開かれてきたのであろう。
それで、親鸞聖人は、往生極楽の方法を尋ねる弟子たちに対して、「念仏は、まことに浄土にうまるるたねにてやはんべるらん、また、地獄におつべき業にてやはんべるらん。総じてもって存知せさるなり」と、そういう方法に対する関心は、今の自分にはもはやなくなったと述べられたのである。そして、「たとい、法然聖人にすかされまいらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずそうろう。そのゆえは、自余の行もはげみて、仏になるべかりける身が、念仏をもうして、地獄にもおちてそうらわばこそ、すかされたてまつりて、という後悔もそうらわめ。いずれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」と述べられた。すなわち、方法さえ間違わねば仏になることができた身が、法然聖人に従って念仏したために地獄におちたというのであれば、「しまった。方法をまちがえた。法然聖人にだまされた」という後悔は当然起こりましょう。しかし、この身は、そんな方法論で何とかなるような身ではなかった。どんな方法も間に合わぬ身だった。そのことを、法然聖人は、身をもって、この私に教えてくださった。そのような出遇いをいただいて、どんな方法も間に合わぬ身に帰ることのできた私にとって、地獄は、この身に定まった終の住み家だと決着していますと、気負いなく、自然に言うことができたのである。。
「善き人にも悪しきにも、同じように」
◆また、恵信尼は、「(法然聖人は)善き人にも悪しきにも、同じように、生死出ずべきみちをば、ただ一筋に仰せられ候いし」と書いておられる。
これを読むとき、私は、中国の曇鸞が書かれた『浄土論註』に、阿弥陀仏の浄土について、「三界の繋業畢竟じて牽かず」と述べられている言葉を思い起こすのである。曇鸞は、この言葉によって、阿弥陀仏の浄土は、衆生のどんな生き方も、行為も、属性も、それに左右されることなく、平等に受け容れる世界であることを述べておられる。人間の生き方や行為による選別がまったくない世界なのだ。どのような生き方をしている者も、阿弥陀仏の浄土の世界においては、障りなく、そのまま平等に受け止められるのだ。そういう世界においてこそ、われらは、始めて、自分の生き方に対しての評価に怯え、振り回されていた心から解放されるのである。
また、印度の天親菩薩は、『浄土論』の中で、阿弥陀仏の浄土を二十九種の功徳で表わされ、その中の二番目に「究竟して、虚空の如く、広大にして辺際なし」という功徳(量功徳)を持っていると述べておられる。つまり、阿弥陀仏の浄土は、われらのどんな生き方も、在り方も、属性も、虚空の如く障りなく、そのまま受け容れるところの、広大にして辺際の無い世界であるということ、阿弥陀仏の浄土においては、受け容れられないようなわれらの属性は、何一つないということを述べているのである。そういう世界が、阿弥陀仏の浄土、すなわち、念仏によってあたえられる世界の特徴なのだ。
われらは、評価の物差しでもって見られていることを少しでも意識するならば、自分のありのままを、そのままさらけ出して真っ直ぐに見ることは決して出来ない。しかし、阿弥陀仏の浄土においては、つまり念仏もうさるる世界の中においては、そういう評価の物差しによる選別が一切ないのである。だから、「ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし」という呼びかけをいただき、阿弥陀仏の世界に帰ることによって、われらは、始めて、自分のどんなおぞましい煩悩も、また、目をそむけずにはおられないような自分の闇をも、目を逸らすことなく、そのありのままを、静かに、真っ直ぐに、見つめることができるのである。
ただ一筋に仰せられ候いし
◆また、恵信尼は、「ただ一筋に仰せられ候いし」と、法然聖人の姿を表現しておられるが、「ただ一筋に」とは、正に阿弥陀仏の無条件の呼び声が、「ただ一筋」なのである。阿弥陀仏は、久遠劫の昔から、われらに向かってただ一筋に、「そのお前のままで、私の所に来い。私は、そのお前を待っている。そして、そのお前を、私は永遠に生きていく。そのお前を、どんなことがあっても決して捨てはしない。だから、もう心配しなくていい」と、呼びかけ続けているのだ。その阿弥陀仏の呼び声のひたすらさが、今この法然上人の仰せのひたすらさとなって現れている。親鸞聖人に向かって、つねに「ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし」と、このこと一つを仰せられる法然聖人の上に、そのような阿弥陀仏のひたすらなる呼びかけを恵信尼は感じ取られて、このような言葉で表現されたのであろう。
◆こうみてくると、親鸞聖人と法然聖人の出遇いについて書かれた箇所の『恵信尼消息』の表現は、本当に凄いという他はない。人間業を超えたものが現れているという感じがするのだ。
外から手を差しのべるのではない
◆「どう生きたらよいのでしょうか」――これは、生きる上での方法論を求める問いである。しかし、「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という呼びかけは、方法論ではないのだ。
人間は、生老病死の身をまぬかれ得ない。それ故、人間は、誰も、最終的には救われない身を抱えている。それ故、方法論では、人間は、最終的には救われないのだ。いかなる方法論にも、最終的には裏切られるのだ。
◆従って、「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という仰せは、いかなる方法論によっても救われることのない人間に対して、外から手を差しのべるのではない。最終的には救われないわれらの身と、不二――(離れず、あたかも一つの存在のようになること)――となって、一身同体となって、生死流転の身を、どこまでも、未来際を尽して生き抜いてくださる、その阿弥陀仏・法蔵菩薩の呼び声なのだ。
念仏もうせの呼び声が聞こえてくる時
◆私は、人生の様々な状況の中で、つねに行き詰まり通しといってもよい。そういう私において、例えば、藤谷純子師が葉書き通信の中に書いておられたように、「私は、あなたを生きていくからね」(大分県宇佐市勝福寺発行『かざはな通信』No79)というような法蔵菩薩の呼び声がふと聞こえてくる。http://www.kouruzan-shoufukuji.com/images/kazahana/79.pdf
あるいは、竹中尚文師が書いておられたように、「阿弥陀様は、この状況をどのようにご覧になっているのだろう」(『自照同人』2019年9・10月号)というような、人間の領域を超えた視点への転換の瞬間がふと訪れる。
生死の現実のただ中で、ふと、そのような瞬間を恵まれる。こういうことが、「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という阿弥陀仏の呼び声が、迷いに彷徨しつつある私に、かすかに聞こえてきた瞬間なであろう。
そして、敢えて言うならば、竹中尚文師が書いておられたところの「阿弥陀様は、この状況をどのようにご覧になっているのだろう」という視点の転換は、阿弥陀仏の呼びかけの「超越的な側面」であり、藤谷純子師が書いておられたところの「私は、あなたを生きていくからね」という法蔵菩薩の声は、阿弥陀仏の呼びかけの「内在的な側面」である。
阿弥陀仏は、生死の海に喘ぎつつあるわれらに、こうして、ある時は外から、ある時は内から、呼びかけ、呼び覚ましてくださるのだなということを、両師から教えられるのだ。
◆親鸞聖人が、百日間の聞法を通して、法然聖人の「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」というおおせから聞き取られた世界は、そのような、われらの如何なる生き方、在り方にも障りなく、不二となって、全責任を負うて、生きてくださる。そういう阿弥陀仏・法蔵菩薩の大悲の世界ではなかったかと思うのである。