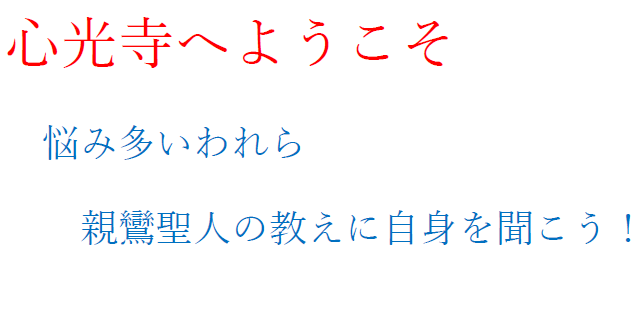(ブログNo.25)一体何が往生するのか?
- bunryu
- 2025年12月5日
「一体何が往生するのか?等の問題について」
■2025年9月17日ジェシー釋萌海さんから次のようなご質問のメールがありました。
「1.内から呼びかけている法蔵菩薩、私にとっては頷ける浄土真宗です。
自己が問われている宗教は他にあまりないでしょう。自分の外にある絶対的な存在を拝むパターンがほとんどです。ありのままで良いよ、という呼びかけから言えば、
You are good enough already, become aware of your deeper self .
※【宮岳意訳】
「あなたは、自分自身の深い自己(もう一人の自分)に目覚めるとき、すでに完全に満たされている。」
2.①成仏やお浄土をどのように受け止めていますでしょうか?
②死後の世界、あると信じていますか?
・真宗学院は魂を否定したのですが、魂がないなら、死後に何が成仏するのか、とずっと違和感ありました。成仏をどのように解釈するかですね?
3.南無阿弥陀仏を称える事は私たちにどのような影響を与えるのか?
南無阿弥陀仏を称えることによって「Our deeper self 」(法蔵菩薩)との繋がりに目覚めると言っても良いでしょうか? 南無阿弥陀仏を称えている自分がいるということは、もう既に The working of Hozo Bosatsu inside ourselves 「我々の奥底から働きかけてくださっている法蔵菩薩のはたらき」が自分に届いている証拠でしょうか?
■2025年10月7日、宮岳よりの返信
1.「魂と往生の関係について」
◇私は拙著の題名を『法蔵魂を呼び覚まされて』としていますが、この場合の魂というのは、魂といっても霊魂のようなものをいうのではありません。
真宗学院の先生が言われるように、仏教では、「常・一・主宰」なる我(永遠に存続し、他によることなく単独で、自分自身を統合し続ける我―アートマン)を否定しています。真宗も仏教である以上、この点については変わりません。しかしそれなら、死後に何が往生し何が成仏するのかという疑問は当然出てくるでしょう。
◇これについては、親鸞聖人の場合、往生というのは、肉体の死後にアートマンのような魂が肉体から分離して極楽世界に生まれるというようなものではありません。『無量寿経』「下巻」の始めの方に次のような経文があります。
「諸有衆生、その名号を聞きて、信心歓喜せんこと、乃至一念せん。至心に回向せしめたまえり。彼の国に生まれんと願ずれば、即ち往生を得、不退転に住せん。唯、五逆と誹謗正法とをば除く」(第二版聖典238頁)
意訳すると、「われら迷いの衆生は、南無阿弥陀仏の名号の呼びかけを聞く時、自我を主体とした今までの自分に死んで、『願生』という、法蔵菩薩の願心を主体とした新しい自己を呼びさまされて、その自己を生きるようになる。そして、救いから除かれた地獄一定の身に腹をすえて生きる者となる。」という経文です。親鸞聖人は、この経文を本願が成就したことを表す文であるとはっきりおっしゃっています。つまり、法蔵菩薩の願いに呼び覚まされて、その願心を生きる「願生(がんしょう)」のことを、「即ち往生を得る」とはっきりと述べておられるのです。ですから、何が往生するのかと言えば、南無阿弥陀仏のお名号に呼び覚まされて、「願生」の自己が新しく生まれ、その自己を生きること。そのことを往生と言うのだと、そういうふうに言うことが出来ると思います。
なお、そうすると、「往生」と「成仏」との関係はどうなるのかという問題が次に出てくると思いますが、この問題については、後日別のブログで考えてみたいと思います。
◇マルティン・ブーバーというユダヤの宗教哲学者は、他者に対する人間のかかわり方に、「我とソレ」という関わり方と「我と汝」という二つの根本的な関わり方があると言われました。「我とソレ」という関わり方は、他者に対して、対象的にあたかも物のように関わる関わり方です。他者に対して物のように関われば、必然的に自分自身も物となっていきます。しかし、人間は本質的にそのような冷たい殺伐とした関係の中を生きることは出来ないようになっているのです。
それに対して「我と汝」という関わり方は、他者に対して、決して対象的に、物のように関わることをしません。他者を、自分にとってかけがえのない存在として、全存在をあげて「あなた」と呼びかけ、一身同体的に関わる関わり方です。
人間は、本質的に、「我とソレ」の冷たい関係の中では生きられないようになっています。これは断言してもよいと思います。にもかかわらず、人間はどうしても「我とソレ」の態度でしか生きられないのです。これは人間の宿業といってよいでしょう。そこに人間の深い悲しみがあります。
その深い悲しみの渦中から、止むにやまれずして生まれてきたのが、「たとえ地獄に堕ちようとも、運命を共にして、どこまでも永遠に一緒に歩み続けていくよ」という稀有の覚悟です。そういう魂が、宿業の底から涌き出てきたのです。それが、「Our deeper self 」(われらの深い魂)、すなわち法蔵菩薩です。不思議としか言いようがありません。人間の宿業の底から、その宿業を永遠に背負うことを誓うという驚くべき魂が生まれてきたのですから。
藤原正遠先生の「いずこにも 行くべき道の 絶えたれば 口割りたまう 南無阿弥陀仏」という歌が思い出されます。絶望の底から、むしろその絶望を母胎として、南無阿弥陀仏という仏さま、法蔵菩薩の誓願が湧き出てくださったのです。『成唯識論』の中で「摂して自体と為して、安危を倶同す」と表現されている法蔵菩薩の大悲の魂の噴出です。これが「我と汝」の呼び声です。南無阿弥陀仏の呼び声です。
◇従って、この魂は、「我とソレ」を基本としたアートマン的な魂「My shallower ego」(私個人の浅い自我) ではなく、「我と汝」という、アートマンを超えた深い魂「Our deeper self」(われらの深い自己)です。つまり、魂にも、「My shallower ego」(私個人の浅い自我)の魂と「Our deeper self」(われらの深い自己)の魂という、質の全く違った二つの魂があると言ってよいでしょう。この二つの魂は、生きている時空が全く違います。「My shallower ego」(私個人の浅い自我)の魂が生きている時空は、ギリシア語でいうクロノス(時計の時間と物理的な空間)の世界です。それに対して「Our deeper self」(われらの深い自己)の魂が生きている時空は、カイロスの世界、すなわち「我と汝」の眼差しの中にあるところの、時計の時間を超えた世界です。その時空のことを、仏教では「劫」と言う言葉で表してきました。親鸞聖人は、法蔵菩薩がご修行される時間のことを、「無始より已来、乃至 今日、今時に至るまで」(第二版聖典254頁)とか、「不可思議兆載永劫に於いて菩薩の行を行じたまいし時」(第二版聖典255頁)というような言葉で表しておられます。そのような時空を生きる法蔵菩薩の願心に目覚め、その願いに呼び覚まされつつ生きることを「往生」「成仏」と言うのでしょう。
②「死後の世界があるかどうかという問題について」
◇このことについては、善導大師の『往生礼讃』の中に、「前念命終 後念即生」(第二版聖典278頁)という言葉があります。この言葉の真意について、親鸞聖人は『愚禿鈔』の中で、「本願を信受するは、前念命終なり。即得往生は、後念即生なり。」(第二版聖典510頁)と明確に述べてくださっています。すなわち、本願を信受した時、前の命が終り、即座に往生という新しい命に生まれ出ると述べておられるのです。
「前念命終 後念即生」についての親鸞聖人以前の了解は、「前念命終」とは、肉体の命が終った時のことを指しています。そして、「後念即生」とは、その肉体の命が終った時、即座に極楽に生まれること、すなわち死後往生を指していると了解されていました。
それに対して親鸞聖人は、「前念命終」とは、肉体の命が終った時ではなく、本願を信受する時、本願を知らずに自力心を主体にして生きていた今までの自分に死ぬ―その時だとされたのです。そして、その時、肉体の死を待たずに、即座に往生の生が始まる。そのことを「後念即生」というのだと明確にされたのです。
このことから、「死」の了解について、親鸞聖人以前と親鸞聖人とでは全く違うということが分かります。親鸞聖人以前の死の了解は、肉体の命の命終する時が死です。ところが、親鸞聖人の場合は、自力心を主体としていた今までの自分が命終すること、それが死なのです。つまり、『歎異抄』第16章に、「日ごろ本願他力真宗をしらざるひと、弥陀の智慧をたまわりて、日ごろのこころにては、往生かなうべからずとおもいて、もとのこころをひきかえて、本願をたのみまいらするをこそ、回心とはもうしようらえ」(第二版聖典780頁)と述べられている回心の時が死の時なのです。
◇さてここで、死についてもう少し立ち入って考えてみたいと思います。私たちが通常考えている「死」は、肉体の命が命終する時です。私たちは、「死」を恐れたり、死んだらどうなるのだろうかと考えたりしています。その場合、「死」は当然あるものとして考えられています。でも、よくよく考えてみれば、私たちがあると思っている死は、実は他人の死であったり、死体であったり、自分もいつか死ぬであろうと想像しているところの死であって、自分自身の死ではありません。
それでは私たちは、自分の死を果して知ることが出来るのでしょうか。それは不可能です。なぜなら、自分が死んだ時、自らの死を知ることの出来るはずの自分はもういないからです。
このことから、私たちが知っていると思っている死は、全て第三人称の死であって、第一人称の死、すなわち自分自身の死ではないということが分かります。つまり、私たちが通常思っている死は、全て死の観念であって、死そのものではないのです。ですから、私たちは、本当は死を知らないのです。私たちは、決して第一人称の死を自ら経験することはできないのです。そういう意味から言うと、誠に奇妙なことですが、私にとって実は死は無いのです。あるのは死の観念だけです。死は観念としてしか存在していないのです。これが肉体の死についての真実です。
このことからはっきり言えることは、死後の世界があるかどうかという議論については、それにいくら答えを考え出したとしても、全て観念にすぎないということです。なぜって、私にとって死は無いのですから死後もない道理です。あるとしたら、それは全て観念に過ぎないということになります。これが肉体の命が終ることを内容とする「死」についての真実なのです。
師の大石法夫先生が、「生きている内は、死にはせんよ」と半分冗談めかして言われたことがありますが、考えてみれば本当にその通りです。
◇ところが、実は私どもが経験できる死が唯一あるのです。それが、親鸞聖人が『愚禿鈔』に書いておられるところの「本願を信受するは、前念命終なり」という「死」です。この死は、肉体の命終を内容とする死ではなく、自我を主体として生きている心の命終を内容とする死です。これが、私どもが唯一経験できる自分の死なのです。
そして、この死の時、直ちに「願生」という、法蔵菩薩の願心に生きる新しい生が始まるのです。願生の生は、親鸞聖人が、道綽禅師の「無辺の生死海をつくさん」(第二版聖典476頁)という言葉を『教行信証』の結びに引文しておられるように、終わることがないのです。
(註・「無辺の生死海」とは、衆生の迷いは果てしなく尽きることがないということ。「尽す」とは、その迷いを逃げずに背負い続けていく法蔵菩薩の願心の歩みを表す。衆生の迷いが尽きないので、その迷いを背負い続けていく法蔵菩薩の願心の歩みも終ることがない永遠の歩みとなる。)
勿論肉体の命の命終の時は来ます。けれども、それは本質的な意味での死ではありません。本質的な意味の死は、本願信受の時既に経験しています。従って「一度死んだら二度死なぬ」という言葉がありますように、もはや死ぬことはないのです。いずれ迎える肉体の死は、生理上の一通過点に過ぎないということになります。
◇このことで思い出すのは、清沢満之先生が死の直前に暁烏敏先生に宛てて書かれた最後の手紙のことです。清沢先生は、亡くなられる五日前、暁烏先生に宛てた最期のお手紙の結びの言葉に、「これでひゅうどろ(註・死んでいくことのユーモア的表現)と致します」と書いておられます。にもかかわらず、そのちょっと前の文では、「一、二点研究したいと思いますから、東方聖書の『英文大経』、佐々木君(佐々木月樵先生のこと)がおあきであれば、拝借したくありますから、よろしくお願いくだされて、ご都合できればご入来の節お貸つけを願います。』(浦田光寿・夷藤保編『清沢満之文集抄録』156頁)と書いておられるのです。一体どうなっているのかと思います。間もなく死ぬと言っているる人が、あたかも死などないかのごとく、「これからこういうことを研究したいと思っているので、今度来る時京都にいる佐々木君から本を借りて持って来てくれ」と、いつになるかわからない先のお願い事を書いておられるのです。同じようなことは、曽我量深先生にしても、安田理深先生にしても、鈴木大拙先生にしても、亡くなられる前の話しとして残っています。このような先生方の最期の言動を聞かせて貰っていると、正に「願生」の生においては、肉体の死は一つの通過点に過ぎないということを感じさせていただきます。
◇「願生」の生について、親鸞聖人は、『高僧和讃』の「曇鸞和尚」において、「如来清浄本願の 無生の生なりければ」(第二版聖典595頁)というふうに「無生の生」と言っておられます。そしてその「無生の生」の左訓として、「六道の生をはなれたる生なり。六道四生に生まるること、真実信心のひとはなきゆえに無生という」(本願寺出版社『浄土真宗聖典全書』二宗祖篇上427頁)という説明を付けてくださっています。つまり、死ぬのは生まれたからであって、生まれなければ死ぬこともありません。「無生の生」といわれる「生」は、人間の迷いの生を受けたのではなく、迷いの生に死んで、久遠の本願に生きる願生の生を受けたのです。だから生滅を離れています。そういう生滅を離れた生が、「無生の生」といわれる「願生」の生なのです。これが「往生」です。
3.最後に「南無阿弥陀仏を称える事と自分との関係という問題」についてです。
この問題に関してジェシーさんは、
「南無阿弥陀仏を称える事は私たちにどのような影響を与えるのか? 南無阿弥陀仏を称えることによって、「our deeper self 」(法蔵菩薩)との繋がりに目覚めると言っても良いでしょうか? 南無阿弥陀仏を称えている自分がいるということは、もう既に The working of Hozo Bosatsu inside ourselves (我々の奥底から働きかけてくださっている法蔵菩薩)のはたらきが自分に届いている証拠でしょうか?」と書いておられます。私も同じように思っています。
それに付け加えて四点ほど述べさせていただきます。
①安田理深先生の講話集に『始めに名号あり』という題名の本がありますように、阿弥陀仏といっても、本願といっても、法蔵菩薩といっても、元は、インドの民衆が称えていた南無阿弥陀仏の念仏の声です。その念仏の声の出所の深さに感動して生まれたものが『無量寿経』なのです。
『無量寿経』に書かれている法蔵菩薩の発願の物語は、『無量寿経』だけではなくて、長い歴史の中で、『如来会』(略称)や『大阿弥陀経』(略称)等々、次々に形を変えながら訳出されています。異訳の『無量寿経』と呼ばれているものです。親鸞聖人は、『教行信証』の中で『無量寿経』を引文される時、異訳の『無量寿経』からも、それに相当する文を並べて引文しておられることが多いです。これは、そういうかたちで、『無量寿経』は、長い歴史の中で南無阿弥陀仏の呼び声を聞いてきた庶民の中から次々と生まれ続けてきたものだということを、確認しておられるのだと思います。
因みに、『無量寿経』は異訳の経典まで含めると、「五存七欠」といって、現在文献として確認できるものが五本あり、題名だけは知られているが文献としては残っていないものが七本あります。つまり、長い時代の中で、南無阿弥陀仏の呼び声は、苦悩の民衆の間で聞き続けられてきたのです。こうして聞き取られて経典になったのが、異訳まで含めた「五存七欠」の『無量寿経』なのです。親鸞聖人が『無量寿経』のことを『大無量寿経』と「大」の字を付けて呼ばれるのは、苦悩の民衆が南無阿弥陀仏の呼び声を聞き続けて、次々と訳出されてきた歴史全体を憶念してそう呼ばれるのです。そういう意味から言えば、七高僧の著された論釈も、親鸞聖人の多くのご著作も、蓮如上人の『御文』も、清沢満之先生や曽我先生のご著作も、いずれも南無阿弥陀仏の声に感動して生まれた物語ですから、異訳の『無量寿経』と言ってよいと思います。
②また、異訳の『無量寿経』は、そういう名前の知られている方々ばかりによって訳出されたのではありません。今までも、今も、これからも、無数の苦悩の民衆が南無阿弥陀仏の呼び声に感動してこられましたし、これからも感動し続けていかれるはずです。庶民は言葉で表現することができませんから、ほとんどが歴史の中に消えていきます。けれども、みんな南無阿弥陀仏を称えてこられた方々なのですから、南無阿弥陀仏の呼び声を聞いてこられた民衆の数だけ、『無量寿経』は生まれ続けてきたし、これからも生まれ続けていくと言ってよいのではないかと思います。
スイスに生まれ、異国の地日本に渡られ、南無阿弥陀仏の道に出遇われたジェシーさんの生涯も、それから、転がるようにして生きてきて南無阿弥陀仏の呼び声に出遇つた私の生涯も、そのほか南無阿弥陀仏の呼び声の中で一生懸命に生きておられる全ての方々も、皆ひとり一人が異訳の『無量寿経』を生み出し続けていると言ってよいのではないかと思います。
③ジェシーさんが書いておられますように、南無阿弥陀仏を称えることは、「My shallower ego」(私個人の浅いエゴ)を生きているわれらに、「Our deeper self」(われらの深い魂)を呼び覚ます活きた働きです。「名号は、生ける言葉の仏身なり」という曽我量深先生の残された言葉を思い出します。
④異訳の『無量寿経』の一つに、『仏説諸仏阿弥陀三耶三仏薩桜仏壇過度人道経』という長い名前の経典があります。通称『大阿弥陀経』と呼ばれている経典です。この中に出てくる次の経文を親鸞聖人は『教行信証』「行巻」に引文しておられます。
「諸天・人民・蜎飛・蠕動の類、我が名字を聞きて慈心せざるは莫けん」
(第二版聖典171頁)
「蜎飛」とは、飛び回る小さな虫、「蠕動」とはミミズのような虫のことです。そういう小さな虫の類まで、南無阿弥陀仏の呼び声が聞こえてきたら、喜ばないものはないと述べられているのです。つまり、南無阿弥陀仏の呼び声を聞くのは、人間理性の浅い表層において起こる出来事ではなく、一切衆生の深層に平等に流れている宗教本能が呼び覚まされて喜ぶ出来事なのだと語っておられるでしょう。正にジェシーさんが書かれているように、南無阿弥陀仏の呼び声を聞くことは、私がどうなろうと、「Our deeper self」(われらの深い魂)、すなわち法蔵菩薩が、常に私と離れず、「今、ここに、こうしている私」にピタリと一枚になって生きていてくださっている―そのことに目覚めることだと言えましょう。
4.補足(まとめ)
〇死後というのは全て観念。在るのは今のこの目覚めのみです。南無阿弥陀仏は、その目覚めを呼び起す呼び声です。
〇南無阿弥陀仏の呼び声によって、「曠劫来流転」の苦悩の身を呼び起されます。そこに、親鸞聖人が「われら」と呼ばれた願生浄土の世界、無量寿のいのちを生きる世界が開かれます。
〇その身は、オギャーで始まってチン(お葬式のかねの音)で終る個人的な身でなく、三世十方の一切衆生の身です。その身こそわれらの帰り場所です。。
〇その「曠劫来流転」の苦悩の身こそ、「我と汝」という大悲の眼差しの中に在る身です。
以上、ジェシーさんの問いに対して、不十分ですが今私の思っていることを、まとまりのないまま書かせていただきました。あくまでも現時点での途中経過の応答に過ぎません。
最後に、大変貴重な問いを与えてくださったことを心から感謝いたします。有難うございました。
南無阿弥陀仏 合掌
(2025年10月10日記す)
(2025年12月5日投稿)