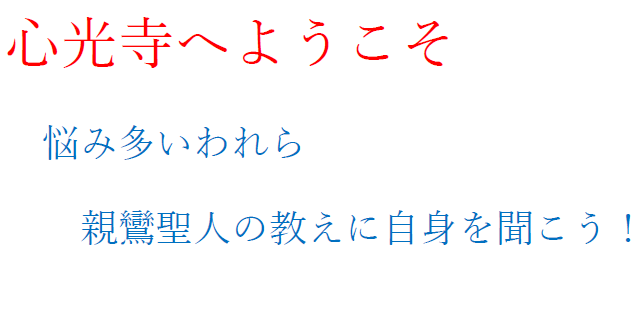(ブログNo.28)再び「回心」について ―Tさんへの手紙―
- bunryu
- 2025年12月20日
T. A. 様へ 宮岳文隆より返信(2025年12月3日付)
今年も師走を迎えました。
9月16日付のお手紙有難うございました。回心について、真摯な率直なご感想を書いてくださいまして有難うございます。色々と忙しい日々が続いた為にお返事を差し上げるのが大変遅くなってしまいまして申し訳ありませんでした。
さて、回心については、『歎異抄』第16章に、「日ごろのこころにては、往生かなうべからずとおもいて、もとのこころをひきかえて、本願をたのみまいらするをこそ、回心とはもうしそうらえ。」と述べられていますが、これについてTさんは、「『もとのこころをひきかえて』というのは、中途半端ではダメで100%ひきかえるということで、」「私にとっては難しいことです。」「大石先生でも39年間かかったとのこと、他の先生方や妙好人の方でも10年以上かかった方が多いそうなので、気長にやっていこうと思います。」と書いておられました。
私は、これを読んだ時、私もそう思ってきたことを思いました。仕事まで辞めて大石先生を聞かせていただこうと思ったのも、「もとのこころをひきかえて、本願をたのみまいらする」という回心の自己を得たかった為でした。
でも、今思うのは、それはいくら時間をかけても不可能ではないかということです。なぜかといえば、それは全く次元の異なる二つの層を一つにしようとしているようなものだからです。ちょうど鉄道の二本のレールを一本のレールにしようとしているようなものです。レールはどこまで行っても二本で、決して一本になることはありません。そのことに気づけば、自分の立っているレールはそのままでいい。「もう一人の自分」という法蔵菩薩のレールが、つねに同時並行してくださっているから大丈夫。―今はそんなふうに思っています。
蓮如上人の言行録である『蓮如上人御一代記聞書』に次のようなことが書かれています。
「衆生をしつらいたまう。しつらうというは、衆生のこころを、そのままおきて、よきこころを御くわえそうらいて、よくめされなし候う。衆生のこころを、みなとりかえて、仏智ばかりにて、別に御したて候うことにては、なくそうろう。」
(『蓮如上人御一代記聞書』初版本聖典867頁、第二版聖典1039頁)
「衆生のこころを、そのままおきて」という所が特に大事だと思います。「ひごろのこころ」については、親鸞聖人が、
「『凡夫』というは、無明煩悩われらがみにみちみちて、欲もおおく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころ、おおく、ひまなくして、臨終の一念にいたるまで、とどまらず、きえず、たえずと、水火二河のたとえにあらわれたり。」
(『一念多念文意』初版本聖典545頁、第二版聖典667頁)
と書いておられますように、息を引き取る寸前まで消えることはありません。でも、「よきこころ」という全く新たなレールは、その「ひごろのこころ」のレールとつねに同時並行して流れてくださっているから大丈夫。しかも、レールは別でも、働きとしては、今、ここに、こうして在る私のレールと離れないかたちで、一枚になって働いていてくださるのです。
蓮如上人は、その働きのことを、「よきこころを御くわえそうらいて、よくめされなし候う。衆生のこころを、みなとりかえて、仏智ばかりにて、別に御したて候うことにては、なくそうろう。」と言っておられるのではないかと思います。このように気づかせていただいて、私はだいぶ肩の力が抜けました。
今時々思い出すのは、西田幾多郎先生のことです。西田先生は、日本を代表するような有名な哲学者ですが、実生活は、想像を絶するような辛いことの連続だったようです。先生には男二人女六人合計八人の子供さんがおられましたが、生前に、長男、長女、次女、四女、五女の五人の子どもが亡くなっておられます。また奥さんも、先生が49歳の時に脳出血で倒れられ、以後6年間病床についたまま、先生が55歳の時に亡くなっておられます。
先生は、そういう中で次のような歌を詠んでおられます。
〇「大いなる 自然の前に ひき出され 打ちたたかれて 立つすべもなし」
〇「運命の 鉄の鎖に つながれて 打ちのめされて 立つ術もなし」
(1922年大正11年52歳 「病院に病児を見舞ひて」と記す)
〇「しみじみと この人生を 厭ひけり けふ此頃の 冬の日のごと」
〇「子は右に 母は左に 床をなべ 春は来れども 起つ様もなし」
これは、先生53歳の時、奥さんと娘さんが左右に枕を並べて病に伏しておられる時の歌です。そして先生55歳の時、その奥さんもとうとう亡くなられます。
〇「冬日影 空しき閨に 射して居り こやりし妻は 此世にはなし」
これは、奥さんが亡くなられた後、奥さんが長いこと寝ておられた部屋に行かれて詠まれた歌です。
こういう歌に接するにつけても、先生は禅の見性体験も得ておられ、その経験を元に深い哲学の思索を持続されましたが、実生活のうえでの辛さはまた別なものがあったということを痛いほど感じます。
そういう中で詠まれたのが、私にとって忘れることが出来ない次の歌です。
〇「わが心 深き底あり 喜も 憂の波も とどかじと思う」
喜や憂の波に翻弄される中で、海の底に目を転ずれば、その底は、波の動乱に左右されず、動乱する波をそのまま静かに受け止め、支え続けてくれています。表面の波は私の宿業ですから、如何とも為し難く、私が息を引き取る寸前まで止まることはありません。しかし、その波をそのまま受け止め支え続ける底も、波と同時並行し続けて下さっています。いわば大谷翔平の二刀流のようなものだなと、いつも私は思っています。
その底とは、久遠劫来の宿業の「この身」のことです。それは元からあったもので、気づけば、すでに私はその上に載せられていたのです。それで、私は今、「到達ではなく回帰」ということを思っています。「宿業の身に帰らせていただく」ということです。同じことですが、「お念仏に帰らせていただく」ということです。
以上、まとまりのないことを書く事しかできませんでしたが、Tさんの真摯なお手紙に対する私からの返信とさせていただきます。
合掌