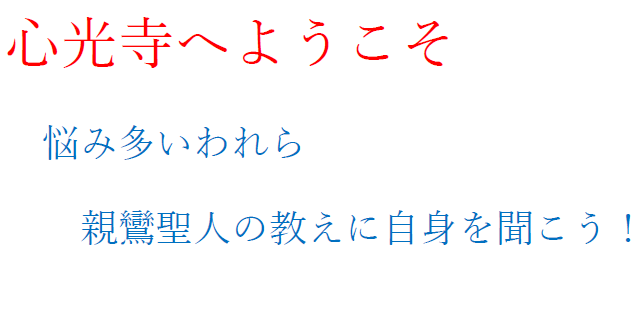No1-法蔵菩薩は永遠の青年
- bunryu
- 2019年10月25日
問いというのは私より大きい
◆大分市のMさんを久しぶりに訪ねた。Mさんは、次々と色んな問いを出してくださるので、私の精神も活性化されるような気がする。
「Mさんとお話ししていると、こんこんと湧き出る清水のように次々と問いを発して
くださるから、これほど心に躍動感を感じることはありません。法蔵菩薩は、永遠の
青年です」
今朝、このような礼状を書いた。礼状を書きつつ、和田稠師に師事しておられた鈴木君代さんが、『自照同人』に次のような文章を書いておられたことを思い出した。
「和田先生は、『問いというのは私より大きいんです』と言われていました。答えは自分に納得のいくのが答えで、問いというのは、そんな私をどこまでも問うものだから、問いの方が私よりも大きいのだと。どうすることもできない私をどこまでも押し出してくれる大きな問いが宗教で、その問いに遇ったおかげで、ますます求め続け、大きな問いに押し出されることによって、いよいよ歩み続け、自分の世界に閉じこもっている私が破られていくのだと」 (『自照同人』2019年1・2月号より)
「どうすることもできない私をどこまでも押し出して、歩ませてくれる大きな問い」。これは、正に法蔵魂そのもののことではないか。
「春逝く人」を読む
◆この礼状を書きながら、蓬茨祖運先生の短い一文「春逝く人」を思い出したので、書き終わった後再読した。それは、次のような文章である。
◇「毎年四月の下旬になると、思い出すことがある。もう二十数年も昔のことだ。六キロばかり離れた村落から使いがきて、『某家の長男が農耕のおり、馬にけられたのがもとで肺浸潤になり、もう助かる見込みがなくなった。ところがその息子が聞きたいというているので、どうか都合して聞かせてやってほしい』とたのむのであった。ことわることもできず、人に聞かせて安心させられるような自信もなかったけれど、自転車で出かけていった。向こうの家に着いてみると、階下には五つの男の子と、七、八歳の男の子と二人、何かして遊んでいるだけであった。『誰も居ないの?』ときくと『二階にいる』というので階段をのぼっていくと、二階の六畳に人びとが集まっていた。
入ってみると病人の足もとの方に村の老人たちが三人ばかり座っていた。両親は右肩の後方に、細君は左の肩に座っていた。父親が少しさがって座蒲団をすすめたのでそこに座った。病人をみると、まったくやせ衰えていて、のどを侵されたのか声もかすれてしまって、耳を病人の口もとによせなければ聞こえなかった。
「何か聞きたいことがあるのか」と問うた。すると「何も聞きたいことはない」というので、唖然とした。
「聞きたいことがあるというのできたのだが、なければそれもけっこうだ」
「いやそれは、村の年寄りたちが毎日きて、苦しいのはいましばらくだ、もうすぐけっこうな浄土にうまれるのだから念仏申せという。自分はなぜ念仏申さねばならないのか、念仏申すとなぜ浄土に生まれるのか。それが自分にはわからないというので、あなたを呼びに行ったのでしょう」
足もとの方に座っている老人たちを見ると、めんぼくないような顔をしてうつむくのであった。それを見ると気の毒なような気分がして、本人が聞きたいなどといつわって、呼びにきたことを責める気もおこらなかった。しかしどうしたものだろうと考えあぐねていると、
「念仏をとなえれば、なぜ浄土へ生まれるのですか」と病人がたずねた。しかし真宗の教義を説明するのは、けっして病人の問いに答えるものではなく、また聞くだけの余裕もないありさまであったので、
「それは私も知らぬ。しかしあなたはこれからどうするのだ」と聞いた。
「私は浄土へなどゆきたくない。ただどうしても死にたくない。それしかないのだ」
「しかし、死にたくないといくらもがいても、やはり死ななければならないのではない
か」
「そうだ」
「それならばまず称えよ。念仏をとなえるとなぜ浄土へ生まれるのか、というわけが
わからねば称えられないとすれば、もう称えるときはないだろう。それは死にたくない
とどんなに思うても、それが役に立たずに死なねばならぬのとかわらぬではないか。
はからいなく称えることが、かえって念仏のいわれにかなうのではないか」というと、「わかりました」と、思いがけなくいうのであった。何がわかったのかこちらが唖然としていると、病人は細い手を胸の上にあわせて、南無阿弥陀仏・南無阿弥陀仏ととなえだした。それをみると涙がこみあげてきたので、そのまま立って部屋をでた。階下におりてみると、小さな二人の兄弟がだれにもかまわれないままうろうろ遊んでいる。どうしても死にたくないという病人の心が胸にしみるのであった。
帰宅してからも気にかかったのは「わかりました」といった病人のことばであった。どう思い返してもわかるようなことをいった覚えはなかった。しかしあのとき、聞きかえす気がどうしてもおこらなかったのである。
翌日、亡くなったことをしらせてきた。その翌日葬式に参った。すると村の老人たちが給仕にきて、先日のお礼をいい、本人はたいへん感謝して家のものにも長い看病の礼をいい、念仏して瞑目した。両親はじめみな悲しみのなかにも喜んでいるということであった。
それから毎年四月になると、春にそむいて逝ったあの人を思い出すのであった。そして念仏とは何であるか、どうして念仏すれば極楽へ生まれるのであるか、あの人にかわって考えようと思った。二十数年たった今になって考えてみると、あの人は自分にとっての善知識であった。
(蓬茨祖運著『真宗の生活感』より)
「ただ称えよ」と、生死の身を呼んでやまない声
◆私がこの話に触れたのは、もう十数年前のことだ。心光寺の報恩講に出講してくださった佐野明弘師(石川県加賀市)が、法話の中でこの話をしてくださった。それ以来私は、この話が心に残り、一度原文を確かめたいと思って、京都に行った折、大谷大学の図書館に行って探し出した。それが、上記の文章である。以来、私は、折にふれては読み返すのである。
この若者は、「わかりました」と言って、念仏もうしつつ命を終えていったのだが、いったい何がわかったのだろうか。いったい何に目覚めたのだろうか。蓬茨先生は、そのことを尋ねて聞法されたと書いておられる。私も、読み返す度にそのことを考えるのである。
今朝再読しつつ、もしかしたら、この若者は、法蔵魂に目覚めたのかも知れないなと思った。法蔵魂とは、法蔵菩薩が、われら衆生の生死の身を、どんなことがあっても捨てずに、未来永劫、運命を一つにして担っていかんと誓われた、一切衆生の身の底に平等に流れているところの魂である。
若者が「わかりました」と言って念仏を称え始めたのは、蓬茨先生が、「念仏をとなえるとなぜ浄土へ生まれるのか、というわけが わからねば称えられないとすれば、もう称えるときはないだろう。それは死にたくない とどんなに思うても、それが役に立たずに死なねばならぬのとかわらぬではないか。はからいなく称えることが、かえって念仏のいわれにかなうのではないか」と言われたのを受けてである。つまり、どれほど死にたくないと思っても、それがかなわず死なねばならない。この厳しい生死の現実の前には、人間の一切の思慮分別心が全く間に合わぬのだ。若者が「わかりました」と言ったのは、何よりもまず第一に、そのことが、痛切に、身に応え、わかったのだ。それと同時に、そういう身をそのまま受け止めて呼んでいるのが、「ただ称えよ」という阿弥陀仏・法蔵菩薩の呼び声だ。「ただ称えよ」という呼び声は、そういう厳しい生死の身と離れずに、ピタッと身を一つにしてくださっている阿弥陀仏・法蔵菩薩の大悲の声なのだ。そのことが、命の最期を迎えている孤独で無力な若者の心に、身に染みるように届いたのではないかと思う。
そうしてみると、「ただ称えよ」の呼び声は、そういう生死の厳しさから逃れられぬわれらの宿業の身そのものから、また、そういう身をご自身の身と為し給うて担うことを誓われた法蔵菩薩の魂そのものから、人間の思慮分別心の一切を経由することなく、直接湧き出た声と言ってよいのである。
若者が、「わかりました」と言って念仏を称え始めたのは、念仏を称えるとなぜたすかるのかというわけがわかったからではない。そのような思慮分別心をまったく経由することなく、どんなに死にたくないと思っても、それがかなわずに死なねばならぬ、この厳しい生死の身から直接湧き起こってくる法蔵魂に促されるままに称え始めたのだ。
こう考えてくると、念仏の信心というのは、まったく人間の思慮分別心を超えている。そもそも、人間の思慮分別心を一切経由せずに起こったものなので、人間の思慮分別心で理解しようとすると、まったく筋違いなことになってしまうのだ。
◆唯円が書いた『歎異抄』(第二章)によると、親鸞聖人は、「念仏は本当に浄土に生まれることができる行なのですか。それどころか、地獄に落ちる業ではないのですか」と真剣に問う弟子たちに対して、「私も、二十年間、必死になってそのことを求めてきましたが、法然聖人にお遇いして以来、そういう問題については、すべてひっくるめて用事のないことになったのです。ですから、今の私は、ただ、法然上人の仰せとなって現れている、阿弥陀仏の『念仏を称えよ』という呼び声にしたがって念仏もうす他に、別の子細はないのです」と答えられたという。この言葉は、往生の方法として念仏は果して有効なのかどうかと問うている唯円に対して、深い衝撃を与えたに違いない。念仏は、何をもっても埋められないものを抱えている人間を、「そのまま来い」と、阿弥陀仏・法蔵菩薩が、師の法然上人を通して、直接呼んでいる声だったのだ。人間の側の方法論の問題などではまったくなかったのだ。そこに、人間の思慮分別心は一切介在する余地はない。「別の子細なきなり」ときっぱりと言い切られる親鸞聖人の言葉によって、唯円は、そのことを決定的に教えられたに違いない。「子細」とは、人間の思慮分別心の一切を指す言葉であろう。私(親鸞聖人)が念仏をもうすのは、その子細を経由していないということである。
法蔵魂は永遠の求道魂
◆人間は、生死の身を決してまぬかれることはできない。さすれば、人間は、どんなに救われたいとあがいても、最終的に救われない身を抱えているのだ。法蔵魂は、そういう身に目覚め、そういう身を捨てずに、どこまでも徹底して担ってゆこうと立ち上がった魂だ。
したがって、中国の善導が表明されたところのいわゆる「機の深信」の言葉、すなわち「自身は現にこれ罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた、常に没し常に流転して、(未来永劫にわたって)出離の縁有ること無しと深く信ず」、これこそは法蔵魂の噴出なのだ。「自身は」とは、、法蔵菩薩が、「自身は」と言っておられるのだ。
「永遠に救われぬ身だ」という自覚は、永遠なのである。これこそ無量寿のいのちである。
「永遠に救われぬ身を生きてゆこう。そこに身を据えて、衆生と共に、念仏の呼び声をどこまでも聞き続けてゆこう」という魂が、法蔵魂なのだ。法蔵魂こそは、永遠の求道魂なのだ。
「春逝く人」の若者は、この法蔵魂に目覚めて、念仏をもうしつつ、永遠の法蔵魂へ帰っていったのだ。今朝、ふとそんなふうに感じた。
「わかりました」の一言を残して逝った若者は今も生きている
◆蓬茨先生が、「春逝く人」を書かれたのは、おそらく1970年代の頃だろう。そうすると、「もう二十数年も昔のことだ」と蓬茨先生は書いておられるので、この若者が亡くなったのは、もう今から七十数年も前のことになる。だが、「わかりました」の一言を残して、念仏を称えながら亡くなっていったこの若者の姿は、その後の蓬茨先生の聞法求道の原動力となって生き続けた。また、佐野先生の法話の中に生きていた。また、今、私の中に生き続けている。おそらく、これからも、この話を聞いた人の中に生き続けていく。人間の肉体は消えてなくなっても、その人の底に連綿として生き続ける法蔵魂は、無量寿だということをあらためて感じる。
【関連サイト】